同棲生活一ヶ月目
『この世界の片隅に』は『火垂るの墓』や『風立ちぬ』につづく現代の反戦映画である。(ネタばれあり)
前回の記事はこちら↓
「この世界の片隅に」という映画が高畑勲氏や宮崎駿氏を凌駕したという声があるようなのでそれについて考えてみようと思う。
「火垂るの墓」との対比

「風立ちぬ」との対比

戦争映画の表現方法もまるで違う。片渕監督は先述した通りであるが、「風立ちぬ」でも分かる通り、宮崎駿は戦争そのものにロマンを感じるタイプの監督で、戦車や軍艦、戦闘機、また機関銃が迸るような好戦的な男たちを描くのを好む。同じ戦争映画を描いていたとしても、表現方法には相容れないような隔たりを感じる。宮崎駿氏自身も自他共に認める反戦主義者であるが、しかしその物語の描かれ方はあまりに矛盾しているようにも感じられる。
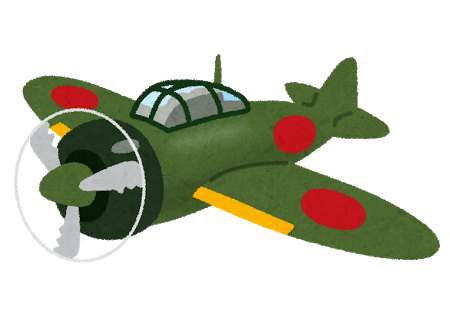
そんな彼を支えたのが当時監督だった高畑勲であり、高畑のアニメ哲学と人徳に触れてようやく居場所を見つけたのではないだろうか。宮崎は劇場アニメ監督として現場を指揮する才能が自分にあるか自信を持てなかったのだと思う。誰も自分について来てくれるものはいなくなってしまう。だからこそ「風の谷のナウシカ」で宮崎駿が劇場アニメ監督として抜擢された時、高畑勲をプロデューサーにと強く推したのではないか。なおジブリ作品にとって久石譲の音楽はすでに欠かすことのできない存在となっているが、久石の音楽を宮崎駿に強く推したのは高畑勲である。
そしてそこに宮崎を指揮する鈴木敏夫という男がいた。ご存知の通り、後のジブリ作品でずっとプロデューサーとして名を冠することになった男である。鈴木敏夫は初劇場映画監督作品である「カリオストロの城」ですでに宮崎駿の才能を知っていた。そして鈴木は宮崎駿を稀代のアニメ映画監督というプレイヤーに育て上げることを決めた。宮崎駿はたしかに指揮者としての才能はなかったかもしれない。しかし鈴木が指揮者となって宮崎の言葉をスタッフに代弁していったのである。結果、プレイヤーとしての宮崎駿の世界観を最大限に追求できる場がもたらされた。そして宮崎駿は鈴木の期待に応えるように、また自らこそがプレイヤー(アニメーター)であると自覚し、宮崎自身が物語の主役であろうと作品世界をとことんまでこだわり、アニメを作り続けようとした。気がつくと彼の映画には宮崎駿という王様しか存在していなかったが。
一方「火垂るの墓」の高畑勲は、作品に身を捧げて、作家性(オリジナリティ)を殺している。作品に身を捧げることを信条としている。テレビアニメ黎明期からアニメに携わり、原作のある作品ばかり手がけてきたアニメーターの宿命であるようにも思う。高畑勲はまるで哲学者のように振る舞う。「ホーホへキョとなりの山田くん」で興行的な大失敗をして14年もの間アニメ映画から干されても、ただじっと我慢をした。宮崎駿が王様なら、高畑勲は音を出さない指揮者のようだ。耳を澄ましながら原作という楽譜を読み取り、映像に韻律を作り、精密に、正確にシーンを並べて、リアリティを積み上げて芸術性を高めていく。映画は芸術であるという一面も併せ持つ。高畑勲の作業は写真のようにその時代や人物の心を映像で切り取り、記録すること。『記録すること』そう、それを高畑勲は自らの命題として据え置いた。
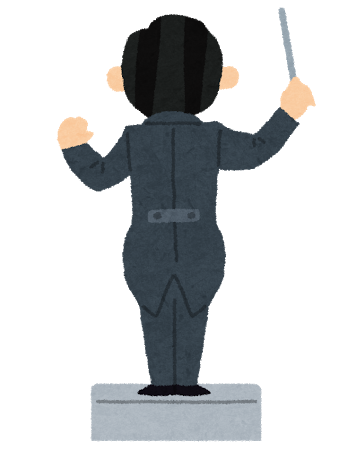
片渕監督は高畑勲に近い指揮者タイプのアニメ監督である。インタビューを読むとどうやら片渕監督自身かなり意識しているようだ。映画に、韻律を作り、正確に、リアリティを上げていく、そこまでは一緒である。しかし芸術性を高めてやろう、また片渕監督からは、片渕須直という名前を後世に残してやろうという野心を、僕はなぜかこの作品から感じられなかった。芸術性や作家性を片渕はあっさりと放棄しているように見える。片渕監督には哲学者というより、戦術家のような匂いがする。流動的に形を変え続ける言うなればサッカーの監督。これまで培ってきたであろう理論や哲学を駆使しながらも、時代の空気を読み取り戦術を変更する。最も旬な「のん」という役者を主演に配し、役者や絵などの個々のパフォーマンスをあげ、最高の組み合わせを考えて、効果的に物語を組み立てていく。結果、最高のパフォーマンスを伴った作品が出来上がる。昨年快進撃したすえに奇跡の初優勝を成し遂げたレスターのような勢いがある。クラウドファンディングで4000万円集まったそうだが、資金と話題性のおそらく双方を集めるためににあえてクラウドファンディングを利用する。現代の映画監督が、現代技法を駆使して、現代の雰囲気にあった映画を作り上げた。片渕監督は今もなお走り続けている監督なのだ。
誰がこの作品の顔になるのか?
役者の声でありながら、アニメ全体に溶け込むように均質性(キャラクター性)を保ちながら、また不安定さを、すずの心情に反映させるという技もやってのけ、「のん」という肉体の容れ物に「のん」自身でありながらも「すず」をすっぽりと容れてしまった。
前回の記事はこちら
感想『この世界の片隅に』のんの役割と反戦映画について(ネタばれあり)
こちらもどうぞ

北條すず 主人公
北條周作 夫
黒村径子 姉
黒村晴美 姉の子
北條円太郎 義母 姑
北條サン 義父 舅
水原哲 初恋?の人 海にウサギが飛ぶ絵を描いてあげた。
白木リン スイカを分けてあげた。遊女
浦野スミ すずの妹
「のん」の演技
あまちゃんは観たことがないのだけど、内側から出てくる純真さをよく出している。声を作らない役者の演技。演技力もあり、作風によく合っていた。片渕監督が惚れ込んだとのことだ。
まず物語が始まって最初に浮かんだのが彼女の声だった。どうして「のん」を選んだのだろう。どうして声優ではない彼女を選んだのか。原作も読まず、事前情報をほぼ持たずにこの映画を観にきた私にとっては「のん」という彼女だけが知りうる情報で、さらにいうなら能年玲奈の演技すら観たことがなかった。レプロとかどこかの芸能事務所を脱退したことが、鑑賞前の私の中で大きくクローズアップされていた。なぜ片渕監督は「のん」こと能年玲奈を選んだのだろう。その疑問は冒頭の5分であっという間に氷解するのだが(これは実際に観てもらうしかないのだが)、アニメで声優以外のキャスティングされるたびに議論になることがあり、ついでなのでそれについて考えてみる。
声優は、声を作る。声優はまず自分自身の声が持つ可能性への発見の後に、様々なパターンの声を作り上げる。声優は声質で配役されることが多く、より多くキャスティングされる(仕事を得る)にはより多くの声を作ることが戦略上武器となるからである。結果、アニメでは尋常とはいえないような声が溢れかえるようになる。そして一方でアニメならではの声も多数生まれる。あにめの主人公は、物語の構造上、あまり特徴のない平均的な無機質な声質が選ばれることが多く、女性ならば大人しい、朗らかな印象を持った声質が選ばれるのではないだろうか。また男性の視聴が多いアニメでは、女性の主演を演じるキャラクターの声質は、男性に媚びたような少し艶のある声に近いものになる。そしてこれは男性声優も当てはまる傾向だ。つまり、アニメ業界の共通観念といってもいい何か大きなフィルターを通すことによってアニメ特有の声というものが出来上がるのだ。
しかしそのようなアニメ特有の声は、視聴する上で雑味となることもある。日常で普段見聞きする声とは異質なものだからだ。『不気味の谷』とでも表現するような感じと言うのだろうか、機械音声に違和感を持つ者がいるのと同様、アニメの声にも違和感を持つことがある。近年では、アニメの普及により、大人も子供も見るようになったためそのような声を聞くことは少なくなってきたが、年配の方には一定数そのような感情を抱くものがいる。映画を見る予告版で例外なくアニメ映画の、劇場で響き渡るその声は、私を居心地の悪い気持ちにさせた。よって、そのような声を取り除くためにあえて、ジブリ映画のように自然な声を得るためにアニメ声優以外から声を求めることも少なくなくないという。
舞台や実写映像を舞台とする役者はどうだろうか。役者は発声や抑揚などのトレーニングはするが、声は作らない。声を作るのではなく、感情を込めることを優先するからだ。このシーンではこうしたいという気持ちを優先する。故に役者の声は身体性を持ったリアルな声になる。演じる役者に声優としてのクオリティが保たれるかどうかという懸念事項は産まれるものの、雑味が生じることはない。アニメで主演を演じる役者には、リアルな容れ物がアニメの容れ物を補完するように作用することを求めるのである。
役者にも声優にも同じことが言えるのだが経験を積んだ者ほど、演技や声質、声調としての最適解を選ぶようになる。ブレない演技とも言えるし、安定した演技とも言える。脇役を固める声優であればブレない演技は、キャラクター性を強化することにな理物語に安定感をもたらすが、主演を演じる人は、常に物語に注目してもらうという別の要素も必要となる。つまりブレない演技に加えて、ズラした演技が必要となるのである。観客を不安にさせるような演技。監督や主役が結託して観客を注目させるために時に、不安定な中で綱渡りをするような演技をすることがある。
アニメや映画、演劇における冒頭の5分は言うなれば主役のものだ。観客は主役に注目するものなのだ。物語に没入するには主役というフィルターが必要だからだ。普段聴いたことのない映像や音楽や声が目の前に飛び込んでくる。そしてチューニングするように観客も物語に合わせてくる。その接点となる作業を主役が果たすのだ。主役を指揮し観客を注目させ続けるために、全体像を把握した優秀な監督が必要なのだろうけども。
「のん」のキャスティングは正解だったのか。言うまでもなく正解だった。おそらくのんは、片渕監督とともにアニメ映画のための声についての研究を行っている。自分の声でありながら、アニメに合った声を作り上げてしまった。声の艶を消し、役者の声でありながら、アニメ全体に溶け込むように均質性(キャラクター性)を保ちながら、また不安定さを、すずの心情に反映させるという技もやってのけ、「のん」という肉体の容れ物に「のん」自身でありながらも「すず」をすっぽりと容れてしまった。
主人公「すず」について
すずが首を傾けたところとか、ぼんやりとしているところは、男性の守りたい抱きしめたいという欲求をうまく惹起していたと思う。一言で言うなら可愛いのだ。水原でなくても抱きしめたくなるだろう。北條家に嫁いだ後も、卑屈さもないし、ずるをしようという気持ちも、径子に仕返ししてやろうと思う心もなかった。また呉に帰ろうと思う弱気な女の子でもなかった。だからこそ余計に健気で可愛らしく感じてしまう。しかし、それが晴美の死によって、正気を失ったすずの姿を見せられることによって、それがすずの強さだったのだと明かされ、健気さは男達の勝手な思い込みなのだと知らされる。「すず」の強さはどこから生まれたのだろう。家族に優しく育てられたこと、兄に厳しく躾けられたこと。北條家でも両親に優しく迎えられたこと。周作に愛され大事にされたこと。水原哲に「普通でいろよ」といわれたこと。そんな色んな出来事がすずを普通であることを強い、正気を保たせた。戦争を通して描かれるすずの世界は朗らかで、悲しくて、素晴らしい。つまり、この世界が無垢で、悲劇的で、可憐であることを指し示している。
絵柄
すずの絵も、こうの史代氏の絵も好かった。本当に良かったなあ。画集があれば買いたいし原画展も見に生きたい。
編集
戦争中の様々なエピソードが織り込まれていて、ボリュームがあった。ほぼ片渕監督の手腕だが、編集で良いエピソードを効率よくつなぎ合わせられるアニメの良さが出た様子。実写だともっと切り取られるのではないか。
楠公飯を作るようす、白木リンの遊郭街での再会、戦艦大和と武蔵の登場、防空壕の中の様子、原爆の様子、空襲警報、晴美が死んですずの右手が失われてしまったこと。子供を連れ去ってきたこと。2年という連載期間のなか時間をかけて調べ上げたこうの史代氏と、それをアニメ映画で映像化するために更に詳細に調べ、まとめ上げた片渕須直の手腕、この二人の出会いもおそらく僥倖だったのだなあと思う。
挿入歌
コトリンゴさん。天空烏龍茶のCMの歌の人だと思い出した。作品の幻想的なイメージ(幼児性)と合致していた。また女性の可憐さを演出していたと思う。晴美を失うところに歌をのせたのは監督の好みだろう。強すぎるほどのあざとさを感じた。言い方を変えると現代的でアニメ(フィクション)であるということを思い出した。夢から覚めて現実に戻ってしまった。そして唄を冷静に聴いていた。「右手のうた」のタイトルは歌手の思いだろう。幼児性と女性性が晴美の死によって断裂してしまう。強い思いが出たのだと思う。たぶんコトリンゴさんの声はこのアニメ映画にとって重要な骨格を担っていた。もし挿入歌がコトリンゴさんじゃなかったら、彼女の声がなかったら、どうなっていたんだろう。片渕監督はこれを計算していたのか? 機会があれば聞いてみたい。
反戦映画かどうか
反戦映画かそうでないかの端的な違いは、戦争で死んでいくことに対しての評価で分かれる。例えば極端な話だが、戦争が起きたのは“仕方がなかった”と少しでも思えるような箇所があれば、それは反戦映画ではない。反戦主義者は、戦争そのものを否定しようとする。生き残るための戦いであるという前提はもとより、戦争にスリリングな命をかけた男たちのロマンであると語ることも否定する。日本の反戦主義者の立ち位置は欧米での菜食主義者と似ているかもしれない。まるで肉の代わりに大豆を使うように、戦いのロマンを語るためには、完全なファンタジーか、近代化する前の時代のものである必要があった。敬虔な反戦主義者は絶対に戦争を起こしてはいけないと語る一方で、戦争という概念すらも封印しようとする思想が見受けられる。
そして上の定義に沿うならばこの映画は完全なる反戦映画である。しかし戦争そのものは否定していない。戦争という概念(構造)を封印しようとはしていない。こうの氏と川淵氏の両者の時代考証を経て戦争の事実を忠実に描こうとしている。
僕はこの映画を見る2、3日前にたまたま『湾生回家』という映画を観ていた。神保町駅を出てすぐのところにある岩波ホールで上映された、『湾生』と呼ばれる台湾で生まれの日本人国籍の人たちの、その後を描いたドキュメンタリー映画である。『湾生』が日本が戦争に負けて中国の領土となった台湾を去って日本に親とともに強制送還され、日本で暮らしていた。彼らの今の姿と、台湾を訪れる時の顔をカメラは追っていた。
その中で、『湾生』が強制送還されて、初めて日本に降り立ったときの気持ちを述べるシーンが現れた。親から日本は素晴らしい国だと言われてきたのに、いざ行って見ると、日本は暗く落ち込んでいて、冷たかったという印象を持ったそうだ。事実、戦後しばらくの間、日本は経済的にも困窮した状況が続いた。人々は希望を失い、陰鬱した雰囲気が漂っていた。台湾はおおらかなのんびりとした人が多く、雪の降らない亜熱帯の気候の温暖な台湾で育ったがために、寒い日本、また勤勉な日本に対してそう思ったのかもしれない。しかしその印象はある意味では、真実だったのだと思う。戦争中は大人も子供も女性も老人も、アメリカに勝って生き抜こうというという気持ちがあったから強く頑張れた。すずも、日本が生き抜くために北條家を守るために頑張ったのだ。しかし、戦争で負けてしまったことでその心の支えはぽっきりと折れてしまう。
そんな状況の中にあって日本人は自尊心を奪われてしまったという者がいる。その植えつけられた劣等感は今もなお続いているのだと言う。高度経済成長を経て国は少しずつ豊かになり豊かになり、その子供達が生まれ国は見違えるように変化していても、日本人としての自尊心は奪われたままなのだ。全ては戦争のせいなのだと言う。
しかし本当に日本人は自尊心を失ってしまったのだろうか。失ったままなのだろうか。人の心は簡単に推し量ることができないものである。また心は決して奪うことのできないものの一つなのではないだろうか。バブルで浮かれてしまった時も、日本人は自尊心を失っていたわけではないだろう。戦後の今もこれまでもずっと日本人の生活があった。たとえ焦土と化しても、大勢の仲間が亡くなっても、生き残った者の心を消してしまうことは出来ない。それが僕が、『この世界の片隅に』ですずさんから受け取った伝言(メッセージ)である。あの世界では、人と人との小さなずれがリアルに描かれている。戦争という背景の前で、一人一人生きていた。
クラウドファンディングのクレジット
すずと周作の恋愛模様について
結婚の祝言でも周作は何も口にせず、黙ったままで、すずと二人きりになったとき、ようやく言葉を交わすほどだった。
「すずさん、傘を持ってきとるかいの」
「ええ、新なのを一本」
「おお、こりゃええ、待っとれや」
と言い、すずが嫁入り道具として持参してきた傘で庇に吊るしてあった干し柿をとり、すずにあげ、そして自分も口の中に入れて平らげる。それを見てすずが「ちゃんと口から食べてじゃけえ安心しました」と冗談を言う。
無口で無愛想だと思っていた周作が実は優しい人だと知り、すずは呉でのきつい労働にも義理の姉の径子のいじめにもへこたれることなく日々の生活をこなしていく。
おっとりとしているけれど、けっして弱音を吐かないすず。北条家の長男として海軍に勤めながら健気なすずをいたわりながら生活を共にする周作。
突然すずの初恋相手の水原哲が水兵として逞しい姿で北條家を訪問してきた折には、北條家の周作がいる前ですずと気心が知れたような仲の良さそうな姿を見せつける。
妻になった自分を呼び捨てにする哲の頭をはたくすずの姿はこれまでに周作が見たことのない姿だ。周作は嫉妬しながらも、戦艦(青葉)に乗り、いつ死ぬとも分からない水原哲の心を推し量っていた。
周作は水原哲を自宅の離れにある納屋に泊め、すずに行火を持たせ「ゆっくりと話でもしてきたらええ」と言って哲の元に行かせた。
すずは言われた通り、哲の泊まる納屋に行火を持っていき、そこで水原と語り合う。寒いからと布団に足を入れと言われる。足を入れて自然と肩を寄せ合う哲とすず。哲に対して抱いていた恋愛感情を思い出し、そして自分の中にあった周作へ愛も知り、一線を越えようとするのを踏みとどまる。
そして同時に周作に裏切られたと思う一方、周作の意思で哲の元に行かされた自分の情けなさに怒りを覚える。愛を試され、また軽んじられたと。すずは激しく周作に怒る。劇中では初めてすずが感情を露わにするシーンである。ここで互いに感情をぶつけ合い、後に信頼という絆が二人の間に生まれた。
こうの史代氏の遊び心で、周作とすずの出会いが人さらいのバケモノの背籠の中という、二人が運命の相手であることを示すというエピソードを入れられた。
広島が舞台について
戦争映画として
続きはこちら



