『この世界の片隅に』は『火垂るの墓』や『風立ちぬ』につづく現代の反戦映画である。(ネタばれあり)
前回の記事はこちら↓
「この世界の片隅に」という映画が高畑勲氏や宮崎駿氏を凌駕したという声があるようなのでそれについて考えてみようと思う。
「火垂るの墓」との対比

野坂昭如原作の「火垂るの墓」は兵庫県西宮市を舞台にした主人公の14歳の清太と4歳の節子の二人の物語である。そこでは戦争の最中、大人たちの都合によって翻弄される無力な子供たちの姿が描かれ、清太は栄養失調ので節子を失い、また清太もまた戦争で父を失い戦争孤児となって死んでしまう。この物語には孤児を守ろうとする大人たちの眼差しが通底している。
一方「この世界の片隅に」は戦争を生き抜く女性たちを物語の焦点としている。原作者もこうの史代氏と女性である。主人公のすずは19歳になっても子供のような風体でぼんやりとしているけれども、北條家に嫁ぎ、呉の女性たちと共にたくましくしなやかに生きようとする。また、ことあるごとにすずにきつくあたる径子自身もさっぱりした部分があり、時折、すずの心を慰めてくれる。
また本作の特徴として、性描写が屈託無く描かれていたことが挙げられる。北條家の結婚式を終えた後の周作との初夜のシーン、防空壕での接吻、水原が北條家を訪れ布団で肩を抱きしめ合うシーン。アニメの主戦場は、テレビでありそのテレビアニメは特質上、子供が見るものであるために性描写に制約が設けられており、エロティックな演出に対して監督もまた観客も不慣れである。宮崎駿氏も高畑勲氏も官能表現に関しては得意とはしていない様子である。おそらく片渕氏も、このような描写を描くことは難しいのではないかと思う。逆説的ではあるがこうの史代氏の原作があってこそのシーンなのではないか。
『この世界の片隅に』という作品は僕が思うに「火垂るの墓」に対するこうの史代氏の、また片渕須直氏の、返歌なのだろうと思う。「火垂るの墓」で描かれた戦争の苦しみを、「この世界の片隅に」によって戦争を生き抜くという希望(エロス)で返したのだ。エロスがこの物語の灯となった。またエロスこそが大人と子供の違いである。周作とすずの夫婦としての営みや、また初恋相手水原晢との再会など、恋愛を物語のもう一つの軸にしたのも理由があるのである。エロス(性)が、子と親を関係を作り歴史を作る。
「火垂るの墓」は子供たちが描かれる一方で「この世界の片隅に」は大人たちが物語の中心だ。この二つの映画に対して子を守ろうとする親と子のように、2枚貝のようにぴったりと合わさっているように感じるのは僕だけだろうか。「この世界の片隅に」という映画は、戦争の鎮魂歌であり、また清太と節子の鎮魂歌でもある。子供が化け物にさらわれるシーンで始まり、周作とすずが孤児(みなしご)を連れて帰るシーンで終わる。子供は希望である。歴史をつなぐ大人たちの希望なのだ。希望そのものである子供には希望は見えないけれど、それを包み込む親の目線が必要なのだ。
凌駕したというか、そういう話ではないのだ。
「風立ちぬ」との対比

そもそも、宮崎駿と片渕監督は全く違うタイプのアニメ監督である。片渕監督はインタビューで言及している通り、リアリティを追求する高畑勲の哲学を持ったアニメ監督である。また宮崎駿も高畑勲の下で長く仕事をしてきたが、リアリティ以上のイマジネーションに従って突き進むタイプのアニメ監督である。
戦争映画の表現方法もまるで違う。片渕監督は先述した通りであるが、「風立ちぬ」でも分かる通り、宮崎駿は戦争そのものにロマンを感じるタイプの監督で、戦車や軍艦、戦闘機、また機関銃が迸るような好戦的な男たちを描くのを好む。同じ戦争映画を描いていたとしても、表現方法には相容れないような隔たりを感じる。宮崎駿氏自身も自他共に認める反戦主義者であるが、しかしその物語の描かれ方はあまりに矛盾しているようにも感じられる。
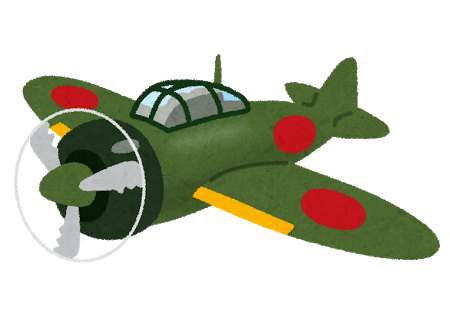
宮崎駿はオタク少年だった。オタクであるがゆえにアニメーターを目指し、またオタク特有のこだわりによって彼自身の腕も磨いていった。宮崎駿は一流の演出家でもあったが、また一流の職人でもあったために、監督後も自分でコンテを切り、また自分で作画をこなしてしまうようなそんな超人的な人物だったそうだ。その圧倒的な力量は伝説となるほどで、テレビアニメ監督としてのデビューは37歳と遅咲きではあったものの、『カリオストロの城』で商業的な成功を収めた後は、第二作で、彼はオリジナル作品をある「風の谷のナウシカ」を手がけることになった。そこで宮崎駿氏が高畑勲氏をプロデューサーに指名して彼がプロデューサーでないと監督をやらないと言った話は有名である。高畑氏はそれまでプロデューサーという職分に就いたことはなく、乗り気ではなかったそうだが、宮崎駿の強い要望によって高畑が再考し承諾したのである。宮崎が指名した理由は明かされず、二人の信頼関係を示すエピソードとしてしか認識していなかったのだが、今から思うと、宮崎駿は自分の性質をよく理解していたのだろう。
宮崎駿がアニメ監督としてデビューしたのが37歳と遅咲きだったのも、その強烈な個性が一因だった。それまで動画マンという身分でありながら圧倒的な力量を見せつけ、監督に口出しをしてシーンを勝手に変更してしまうことがよくあったのだという。そのため監督や他の動画マンの反感を買うことも少なくなかった。
そんな彼を支えたのが当時監督だった高畑勲であり、高畑のアニメ哲学と人徳に触れてようやく居場所を見つけたのではないだろうか。宮崎は劇場アニメ監督として現場を指揮する才能が自分にあるか自信を持てなかったのだと思う。誰も自分について来てくれるものはいなくなってしまう。だからこそ「風の谷のナウシカ」で宮崎駿が劇場アニメ監督として抜擢された時、高畑勲をプロデューサーにと強く推したのではないか。なおジブリ作品にとって久石譲の音楽はすでに欠かすことのできない存在となっているが、久石の音楽を宮崎駿に強く推したのは高畑勲である。
そしてそこに宮崎を指揮する鈴木敏夫という男がいた。ご存知の通り、後のジブリ作品でずっとプロデューサーとして名を冠することになった男である。鈴木敏夫は初劇場映画監督作品である「カリオストロの城」ですでに宮崎駿の才能を知っていた。そして鈴木は宮崎駿を稀代のアニメ映画監督というプレイヤーに育て上げることを決めた。宮崎駿はたしかに指揮者としての才能はなかったかもしれない。しかし鈴木が指揮者となって宮崎の言葉をスタッフに代弁していったのである。結果、プレイヤーとしての宮崎駿の世界観を最大限に追求できる場がもたらされた。そして宮崎駿は鈴木の期待に応えるように、また自らこそがプレイヤー(アニメーター)であると自覚し、宮崎自身が物語の主役であろうと作品世界をとことんまでこだわり、アニメを作り続けようとした。気がつくと彼の映画には宮崎駿という王様しか存在していなかったが。
映画には総合芸術でありながら、突き詰めれば監督のものであるという考え方がある。スピルバーグ、コッポラやキューブリックをはじめとして、日本でも黒澤明を旗手として世界的な映画監督が次々と登場していた。そこに新たにアニメ映画監督として宮崎駿の名が加えられることとなった。宮崎駿は「もののけ姫」のヒットを契機にアニメ監督と同時に映画監督として名を広め、さらに地位を築いていく。彼の知名度が上がるにつれて映画監督としての宮崎駿は徐々に大きくなった。映画監督であらんとし、作家性を追求していった。オリジナル作品こそが彼の真骨頂であると彼もまた周囲も認識していた。自分というフィルターを通して描くことにこだわっている(こだわらざるを得ないのかもしれない)。また自身がプレイヤーであるという意識も決して忘れない(忘れられないのかもしれない)。もちろんそこに調和はなかった。それは息子吾郎に対しても同様だった。それが宮崎駿という男である。
一方「火垂るの墓」の高畑勲は、作品に身を捧げて、作家性(オリジナリティ)を殺している。作品に身を捧げることを信条としている。テレビアニメ黎明期からアニメに携わり、原作のある作品ばかり手がけてきたアニメーターの宿命であるようにも思う。高畑勲はまるで哲学者のように振る舞う。「ホーホへキョとなりの山田くん」で興行的な大失敗をして14年もの間アニメ映画から干されても、ただじっと我慢をした。宮崎駿が王様なら、高畑勲は音を出さない指揮者のようだ。耳を澄ましながら原作という楽譜を読み取り、映像に韻律を作り、精密に、正確にシーンを並べて、リアリティを積み上げて芸術性を高めていく。映画は芸術であるという一面も併せ持つ。高畑勲の作業は写真のようにその時代や人物の心を映像で切り取り、記録すること。『記録すること』そう、それを高畑勲は自らの命題として据え置いた。
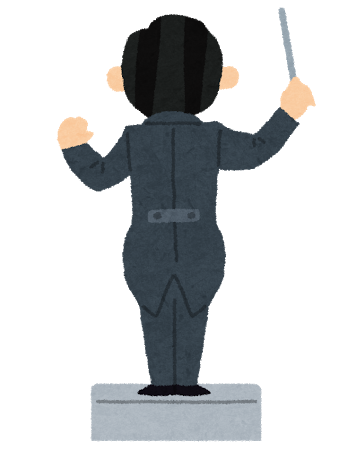
片渕監督は高畑勲に近い指揮者タイプのアニメ監督である。インタビューを読むとどうやら片渕監督自身かなり意識しているようだ。映画に、韻律を作り、正確に、リアリティを上げていく、そこまでは一緒である。しかし芸術性を高めてやろう、また片渕監督からは、片渕須直という名前を後世に残してやろうという野心を、僕はなぜかこの作品から感じられなかった。芸術性や作家性を片渕はあっさりと放棄しているように見える。片渕監督には哲学者というより、戦術家のような匂いがする。流動的に形を変え続ける言うなればサッカーの監督。これまで培ってきたであろう理論や哲学を駆使しながらも、時代の空気を読み取り戦術を変更する。最も旬な「のん」という役者を主演に配し、役者や絵などの個々のパフォーマンスをあげ、最高の組み合わせを考えて、効果的に物語を組み立てていく。結果、最高のパフォーマンスを伴った作品が出来上がる。昨年快進撃したすえに奇跡の初優勝を成し遂げたレスターのような勢いがある。クラウドファンディングで4000万円集まったそうだが、資金と話題性のおそらく双方を集めるためににあえてクラウドファンディングを利用する。現代の映画監督が、現代技法を駆使して、現代の雰囲気にあった映画を作り上げた。片渕監督は今もなお走り続けている監督なのだ。
誰がこの作品の顔になるのか?
しかし私は「この世界の片隅に」から片渕監督自身のイズム(作家性)を感じることは残念ながらなかった。おそらくこの監督は今後もアニメ監督として走り続け、様々な作風の作品を作り続けるのではないかと想像する。(インタビューを読み返すとそう読み取れる記述もある)映画業界の不遇のせいだとも言えるが、監督として一流の才能がありながら、宮崎駿や高畑勲や庵野秀明らと肩を並べるほどのカリスマを持つには、ほんのもう少し時間がかかるだろう。では誰がこの作品の顔になるのだろう。原作の漫画家のこうの史代氏だろうか。コトリンゴ氏だろうか。『風の谷のナウシカ』で宮崎駿、高畑勲、鈴木敏夫、久石譲という傑出した才能が集まったように、この作品でも傑出した才能が集まったことは確かである。すると意外な人物の名前が浮かび上がる。能年玲奈である。思い返せば彼女は色々なものを食ってのし上がってきたように思う。彼女は「あまちゃん」を食らい、リプロという所属事務所を食らい、今度は「この世界の片隅に」を食らって踏み台にしようとしている。悪運を彼女は持っている。思えば能年玲奈という存在は不思議な存在である。誰もなし得なかったことをしようとしているのだから。
戦争映画であること、ファンタジー映画であること、恋愛映画でもあること、筆やペンが原作者の気持ちを代弁するような物語をつなぐ重要なファクターになっていること。構造上ではあるが『風立ちぬ』と『この世界の片隅に』は似通っている部分がある。残念ながら、こうの史代氏によって「この世界の片隅に」が連載されていた期間は2007年から2009年で、「風立ちぬ」は2013年とのことで、少なくともこうの氏が『風立ちぬ』を意識して作ったとは考えられない。『火垂るの墓」は有名な作品だからこちらの作品から、こうの氏が影響を受けた部分はあるかもしれない。また宮崎駿氏がどこかで『この世界の片隅に』という作品を読んでしまったがために、無意識のうちに参考にしてしまった可能性も僅かながら考えられる。実際はどちらでも構わないのだけど、『風立ちぬ』と『この世界の片隅に』にはやはりどうも完全に分けて考えることのできない見えない類縁関係のようなものがあるようだ。宮崎駿氏によって、『火垂るの墓』につづく反戦映画をこの時代にまた描いていいのだろうか、そういった小石のような瑣末な議論を宮崎駿が一度全て吹き飛ばした。『風立ちぬ』は『この世界の片隅に』を世に広めるための人あらざる者が投げた布石だったのではないか。そんな考えがふと僕の脳裏に思い浮かんだ。
前述を繰り返す形になるが
役者の声でありながら、アニメ全体に溶け込むように均質性(キャラクター性)を保ちながら、また不安定さを、すずの心情に反映させるという技もやってのけ、「のん」という肉体の容れ物に「のん」自身でありながらも「すず」をすっぽりと容れてしまった。
これほどまでに観客をドキドキさせて、ハラハラさせて、鑑賞後も注目を浴びた人間がいただろうか。それをしかも初の主演アニメ作品でやってのけたのである。のん以外にその偉業をやってのけた者の顔を僕は知らないのである。
では、あらためて3つの映画の関係について考えてみる。
(了)
前回の記事はこちら
